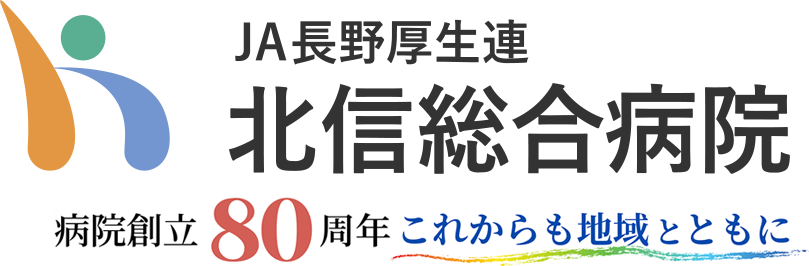about病院について
チーム医療
緩和ケアチーム
緩和ケアチームは、がんなどの病気を抱える患者さんとそのご家族の、身体の症状や気持ちのつらさなど和らげ、その方らしく生活ができるように主治医や担当看護師と協力して支援させていただいています。
緩和ケアチームの構成メンバー・活動
| 緩和ケア医師 | 痛みなどの身体のつらい症状を緩和します |
| 精神科医師 | 不眠や、落ち着かない気持ちなどを担当します |
| 看護師 | 生活に合わせて症状を和らげる方法を患者さんご家族と一緒に考え、患者さん、ご家族さんが安心して過ごせるようにお手伝いします |
| 薬剤師 | お薬の特徴や使い方についてアドバイスします |
| 管理栄養士 | 患者さんの病気や身体の調子に合わせた食事を工夫します |
| メディカルソーシャル ワーカー | 医療費や介護保険など、社会生活への支援などを行います |
| 臨床心理士 | つらい気持ちなどをお聞きします |
緩和ケアチームより
患者さんおひとりで悩まず、ご家族だけで心配するのではなく、周囲のスタッフにお気軽にご相談ください。緩和ケアチームでは一緒に考え、心と身体のつらさを和らげるためにサポートしていきたいと思っています。サポートをご希望の方は主治医、担当看護師にご相談ください。
緩和ケアチームのご利用には健康保険が適用されます。
排尿ケアチーム
排尿ケアチームは、膀胱留置カテーテル抜去後の排尿障害を改善するために、泌尿器科医師、看護師2名、理学療法士、事務で結成されたチームが包括的なケアを提供することを目的とし活動しています。
手術や治療で入院後、膀胱留置カテーテルを入れることがありますが、カテーテルを長期に留置すると尿路感染や下部尿路機能低下などを合併してしまいます。1日でも早く膀胱留置カテーテルを抜去し、下部尿路機能低下を防止するとともに、自力での排尿管理ができることを目指しています。
尿道カテーテル抜去後、「おしっこが出ない」「おしっこに何度も行く」「失禁する」「おしっこが出たことを伝えられない」などの悩みを、主治医や看護師、患者さんと一緒に考え、個々に合わせた排泄方法や排泄の道具、環境作りをお手伝いさせていただきます。
毎週火曜日の午後活動しています。現在は1病棟の介入ですが、今後は院内へ広めていきたいと考え準備しています。
認知症ケアチーム
認知症と診断された方、高齢の方、もの忘れのある方は、入院による環境の変化、身体の不調や慣れない治療により混乱を起こしやすく、入院生活や退院後の日常生活に支障を来たすことがあります。
認知症ケアチームでは、そのような患者さんが少しでも安心して療養生活を送っていただけるように、入院中・退院後の生活をサポートいたします。
チームメンバー
- 神経内科医師(認知症専門医)
- 認知症看護認定看護師
- 社会福祉士
- 看護師
活動内容
- チームによる病棟ラウンド(1回/週)を行い、カンファレンスを開催し、症状軽減を図るための適切な環境調整、ケア方法やコミュニケーションなどを検討します。
- 必要に応じて、ご家族からの認知症ケアに関するご相談に応じます。
- 院内の職員に対し研修会を開催します。
褥瘡対策チーム
特徴
褥瘡は、身体に加わった力(圧迫・ずれ)によって骨と皮膚との間の組織の血流が低下し、その状態が一定時間継続すると皮膚損傷を起こし褥瘡となります。褥瘡の発生危険因子は、骨の突出の程度や皮膚の脆弱性などの局所因子、ADL(日常生活動作)の低下や栄養状態など全身的因子、ベッドの硬さや介護力・看護力などの環境要因がかかわってきます。ねたきりの高齢者に発生するイメージがありますが、急性期病院では高度医療による長時間OPEや重傷者が多いため、褥瘡発生危険リスクは決して低くありません。そのため、他職種で構成される褥瘡対策チームが必要となります。当院では、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、事務職員と協働し、褥瘡予防、褥瘡の早期治癒の為に褥瘡対策チームを組織して活動しています。
褥瘡対策チームの組織
数人の褥瘡対策チームでは、多くの入院患者さんの褥瘡対策を把握することはできません。そのため、褥瘡対策チームを2つに分けて組織化し、入院患者さんにきめ細かく対応しています。2つの組織とは、全病院的な視点で対策を検討する「褥瘡対策委員会」、各病棟の専任の看護師で構成され褥瘡対策を実行する「看護部褥瘡対策委員会」があり、お互いに連携をとって活動しています。
褥瘡対策の実際
入院患者さんについては、入院時に褥瘡発生リスクアセスメントを行い、リスクによってポジショニング方法、体圧分散マットレスの選択、失禁や脆弱な皮膚に対するスキンケア、栄養状態の改善、ADL(日常生活動作)の維持・拡大などの対策を行っています。
褥瘡回診・ラウンド
D3(皮下組織を超える)以上の褥瘡患者に対し、チームで回診をしています。病棟看護師とカンファレンスをしながら治癒環境の整備にあたっています。褥瘡の創の評価DESIGN-Rでの評価や、創の写真撮影、褥瘡対策の実施の評価として体圧分散マットレスの適否、ポジショニングクッションの種類や数、介助グローブの設置、日常生活自立度と危険因子の再確認を行っています。
褥瘡外来
第2・4木曜日の午前、形成外科外来では、褥瘡患者さんの診察も行っています。原則として積極的な入院受け入れはしておりません。褥瘡患者さんは、外来にて診察・処置を行い、治療方針をたてて、各施設や在宅でのケアが継続できるようにしています。
栄養サポートチーム
栄養サポートチーム(NST:Nutrition Support Team)の役割
- 栄養アセスメントを行い、栄養管理が必要かどうか判定する。
- 適切な栄養管理が施行されているかどうかチェックする。
- 各患者に最もふさわしい栄養管理方法を指導・提言する。
- 栄養管理に伴う合併症を予防・早期発見・治療する。
- 栄養管理上の疑問に答える(コンサルテーション)。
- 資材・素材の無駄を削減する。
- 早期発見や社会復帰を助け、QOLを向上させる。
- 新しい知識を啓発する。
NSTの役割は、患者に適切な栄養管理を行うとに加え、病院スタッフへの教育、経費節減にまで及んでいます。
当院の活動内容
NST回診
週1回(木曜日15:00~)医師・薬剤師・看護師・管理栄養士・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・歯科衛生士のチ-ムにより各病棟該当患者様の回診を行っております。

各部門の役割
医師
- 対象患者様の問題点の提示
- 栄養療法に関するプランニングの最終的な決定
- 評価
看護師
- 対象患者様の抽出
- 栄養状態・摂食状況の継続的な把握
- 静脈・経腸栄養ルートの管理・維持
- 栄養管理に問題のある患者様の提示・問題症例の抽出
- 経口栄養への移行推進(嚥下・摂食障害訓練へのアプローチ)
- NST回診前の身体計測
- 回診時の患者様の状態や、アセスメントしたことのプレゼンテーション
- 管理栄養士と連携をとり、食事内容の選択や、形態の工夫
- 生活状況を踏まえた退院時指導(患者様・家族様)
看護師は食事の時間のみならず、24時間患者様のベッドサイドにいるという立場であり、実際に患者様の身体に触れ、その変化に気づき、看護師だからこそできる栄養管理に関する情報、また全身状態に関することを、チーム全体に提供する役割があります。そして、実際に食事の介助、経腸栄養剤の投与、静脈栄養剤の投与と、栄養療法の実践を行なっています。
薬剤師
- 対象患者様の抽出
- 栄養薬剤・栄養輸液メニューの提案、指導
- 栄養輸液・混合輸液の投与法の管理
- 患者様・家族様への栄養薬剤の説明と服薬指導
医薬品に限らず、健康食品などの新しい情報も多く、患者様の医療スタッフへの専門的なニーズは増えていると思われます。
当院で採用されている経腸栄養剤、高カロリー輸液などのカロリー、含有ミネラル量、特徴などを表にまとめました。NSTのラウンド時に、その表を用いることで、各スタッフが情報を共有し、患者様に、より適した経腸栄養剤や高カロリー輸液をNSTから提案できるようにしました。
臨床検査技師
- 検査値からみた低栄養状態の入院患者様リスト提示
(患者様基本・検査・処方・注射・食事・手術等) - 検査データの情報処理
- 検査データの解析
- 追加すべき検査、検査の選択、検査の必要性等
管理栄養士
- 栄養アセスメント(基礎エネルギー量及び必要エネルギー量を算出)
- 栄養投与経路及び栄養剤の提案
- 栄養摂取量のモニタリング
- 栄養関連の情報提供
理学療法士
担当している患者様のリハ情報(粗大運動・身体認知機能、移動能力)を適宜NST回診の場で提供することにより、検査データとの整合性をスタッフ全体と共有していきます。リハ場面・生活場面での情動意欲などの行動変容を報告することで、生活を想定した栄養管理の助言や提言に繋げます。また、NSTを通じて生活の基盤となる、摂食活動における身体機能・姿勢動作の重要性について、PTの立場から検証し、他職種とのより強力な連携体制の構築に努めていきます。
言語聴覚士
嚥下障害は「食物を口から食べられなくなること」で、加齢や脳血管疾患等の原因により生じます。嚥下障害があると、水分や栄養が摂取できなくなり脱水や栄養不良をおこしたり、また、食物が気道に入ってしまう誤嚥により肺炎や窒息など身体に重大な影響をひきおこすことにもなります。食べるためには、口唇・舌・咽頭など嚥下に関係する各部分の運動機能に全般的認知能力・身体機能が関わりあっています。言語聴覚士は、患者様の嚥下障害がどの段階で生じているのか評価をし、口腔の運動機能改善のためのアプローチをおこなうとともに、できるだけ経口摂取ができるよう、姿勢、嚥下の方法、食物形態の工夫などについて関係職種と協働して支援をおこなっていきます。
作業療法士
NST回診に参加し、OT評価(身体機能、精神機能、ADLなど)を提供し、情報を共有しています。NSTの視点にリハビリ的な視点を追加することで入院生活上の活動状況からみたNST介入が可能になると思われます。共有されたNSTの情報を参考にし、ADL面等へのアプローチを作業療法計画に追加、反映させることもあります。また、食事動作の介助量を軽減するために自助具、高次脳機能障害の理解と対応等食事場面に関わる作業療法的なみかたの情報や知識の共有にも努めています。
歯科衛生士
- 歯科治療が必要かどうかの判断
- 口腔ケア方法の提案・指導
- 窒息の危険があるかの判断
「食べる」入口であるお口の状態を把握し、上記の内容について患者様の状況にあわせて行います。これにより口腔機能低下や誤嚥性肺炎のリスク軽減、窒息の予防にもつながり、「安心して安全においしく食事ができる」ための口腔環境を整えるお手伝いをします。
一般向け情報
栄養サポートチーム(NST:Nutrition Support Team)とは?
米国において1960年台、hospital malnutrition が社会問題となりました。
栄養サポートチームは,1970年代初頭、中心静脈栄養法(TPN)の適応判定と適正実施を目的として米国のボストンで誕生し、TPNの普及とともに世界中に伝播しました。
一方、欧米の栄養サポートチームが専属チームであったため、わが国ではその普及は拒まれましたが、1998年わが国独自の栄養サポートチーム運営システムPotluck Party Method (PPM:持ち寄りパーティー方式/兼業兼務システム)が考案され、これを契機に全国の医療施設で栄養サポートチーム設立の機運が高まり、2005年12月末には,少なくとも684の施設で栄養サポートチームが稼働するようになりました。
栄養サポートチームは栄養管理を合理的に実施するために、専門的知識および技術を有する人員で構成されたチームであり、栄養管理は各医療スタッフがそれぞれの専門的知識を生かし、チームを組んで実践していくことを目標としております。よって低栄養など栄養管理の必要な患者様に医師・薬剤師・管理栄養士・臨床検査技師・リハビリテーションスタッフなど専門スタッフと医事課等の事務スタッフが連携を持ち、それぞれが知識や技術を出し合い、当院でも2005年より稼動し現在に至っております。各職種ともNSTは専属ではなく、兼業兼務システムをとっており最良の方法で患者様の栄養支援を行っております。
栄養サポートチームの目的
- 栄養異常・栄養障害のある患者の識別
- 詳細な栄養アセスメント(各種計測データを基に)
- 安全で効率的な栄養治療の実施
- 治療効果の評価
病院関係者の方
NST関連資格
TNT研修会受講修了者 医師2名
NST専門療法士
・NST看護師 2名
・NST専門薬剤師 1名
・NST専門臨床検査技師 1名
・NST専門管理栄養士 1名
計 5名
当院NSTの活動状況
- 月曜日
低栄養入院患者抽出 (Alb 3.0g/dl以下)
(1)(臨床検査科→看護部長→各病棟師長→各病棟看護師)
(2)(臨床検査科→栄養科) - 木曜日
15:00〜NST回診
呼吸サポートチーム
RST(呼吸サポートチーム)とは、主に人工呼吸療法を受ける患者様の安全管理、人工呼吸器からの早期離脱に向けて活動を行っています。チームメンバーは、医師・看護師・理学療法士・臨床工学技士・歯科衛生士などの多職種で構成され、各専門分野の立場から患者様の支援をしています。
また、院内外の呼吸ケアに携わる医療者を対象に研修会を開催し、呼吸ケアの質の向上を目指した活動もしています。
ICT(感染対策)チーム
ICT(感染対策)チームについて
感染対策チームは医療に関連する感染症を減らすことを目標としたチームであり、当院でも医師、薬剤師、検査技師、看護師の4職種で構成され、それぞれ専門的知識を活かし、病院長直属の組織として活動しています。
感染対策のため組織の運営、病院ラウンド、感染症発生状況の把握、職員の教育や相談対応、マニュアル作成、設備管理、廃棄物管理などを行い、感染症の予防に努めています。感染対策チームの看護師は専従として配置され、発生時には集団発生につながらないように迅速に行動できる体制を整えています。
感染対策チームは、院内だけではなく院外も目を向けています。高齢者施設や住宅においても、感染対策が推奨される取組が必要であり、治療やケアを提供するのであれば、標準的な予防策は必須です。そのためには教育の機会が必要になりますので、ご要望がありましたらご相談ください。
感染対策チーム構成
- 医師
- 看護師
- 薬剤師
- 検査技師